児童演劇「義民助弥の物語」





助弥さんが住んでいた長野市古牧地区の子どもたちが通う小学校は、現在3校あります。古牧小学校、緑ヶ丘小学校、南部小学校の3校です。
この3校で毎年順番に、児童演劇「にとはちさま」を公演しています。
演技指導は、アマチュア劇団員の小池晃弘(劇団空素)が担当。最近では、かつての教え子達が大人になり、一緒に指導にあたってくれています。
公演前日は、スタッフが夜中までかかり会場作り・舞台作りをします。小学校の体育館とは思えないほどの、立派な劇場に仕上げます。
照明はプロの舞台会社に依頼をし、音響も大掛かりな機材を持ち込み、衣装やメイクも本格的です。
その歴史は、2002年の古牧小学校での第1回公演からはじまり(新型コロナウィルスの出現により2020年、21年の公演は中止)今年の2024年の緑ヶ丘小学校での公演で21回目を迎えました。
練習風景はこちら






100人越えの舞台も、10人で演じた舞台も どちらも最高!!

演じる児童は、その当番校の高学年(4、5、6年生)です。希望者であったり、代表となったクラス全員であったり、または演劇部であったり、6学年全員で演じたりと、その年によって、学校によって様々です。
最も大人数の時は、総勢129人。最少人数の時は、10名で舞台を作り上げました。
大人数で作り上げる舞台は、それはそれは迫力があり、心が震えるほどの感動を味わうことが出来ました。また、少人数で作り上げる舞台は、一人二役で役をこなし、人数が少ない分、一人一人が全力で声を出します。助弥さんの思いが、演者の熱量が、ちゃんと観客に伝わる素晴らしい舞台になりました。
各小学校で3年に一度回ってくる「にとはちさま」ですので、1、2、3年生の子たちは、3年後、4、5、6年生になった時に自分が演じるチャンスが回ってくるわけです。
3年前公演を見て、「自分はこの役をやりたい!」と決めて実際に参加してくれる子も多くいます。
自然と受け継がれる「にとはち魂」
この活動の中で、最も感動することのひとつに、OB・OGの子どもたちの姿があります。「にとはちさま」を経験して、小学校を卒業していったOB・OGの子どもたちが、毎年自然と集まってきて、後輩の子どもたちに演技指導をしたり、舞台づくりのお手伝いをしたり、本番当日の衣装の着付けやメイクを手伝ってくれたり、、、という、とても美しい光景を見ることが出来るのです。
こうして、にとはちさまの物語だけではなく、にとはちさまが残してくれた「誰かの役に立ちたいという義の心」も、演じた子どもたちによって自然と引き継がれて行き、2002年から2024年の間に21回(年度によっては、地域用・学校用の2回公演をしていた時期もありますので、公演回数は30回を超えています)の公演を果たすことが出来ました。
今年度(2024年度)は、緑ヶ丘小学校の4年生~6年生の17名がとても素晴らしい舞台を披露してくれました。その様子はこちら!
来年度は南部小学校の番です。
どんな子どもたちが集まってくれるか、今からとても楽しみです(*´з`)
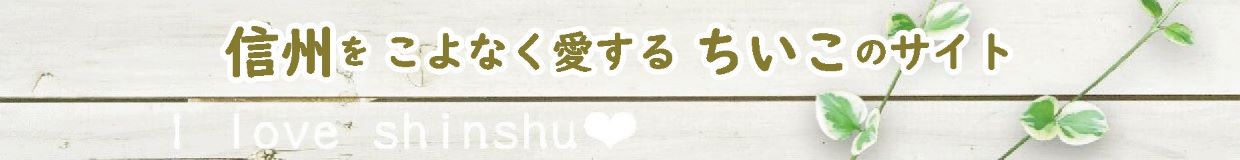


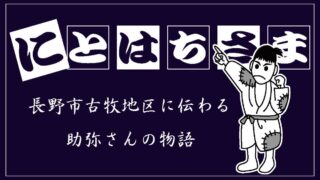
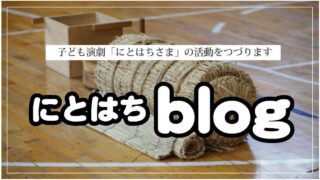

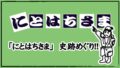

コメント
はじめまして。私は普段長野市にいないのですが、長野市の出身で古牧小学校の学区に実家があり、今は両親もなくなりましたが、その実家を受け継いでおります。11月の信毎で『にとはちさん』の絵本が出たという記事を読み、なんとやっと今日平安堂で手に入れることができました。このHPもこの本から知りました。実は私の父はこの児童劇の立ち上げ、第1回平成14年古牧小学校での劇(古牧地区市制100周年記念事業)にかかわっていました。当時父は古牧地区の社会福祉協議会の会長でした。
父がすごく力を入れていたのを覚えていますが、不肖の娘はそのころはあまり関心がありませんでした。保存会の活発な活動のことや。3小学校を順繰りに今も3年に一度上演しつづけていること、そしてこの絵本になったこと、私も初めて知り。父の仏前に報告しました。初めに古牧で演じた子どもたちはもう中年のおじさんおばさんたちですね。OB・OGの中にはその子たちもいることでしょうね。民話というのはとても大事なその時代や社会のドキュメントですね。絵本にされたことの意義は大きいと思います(私は子どもの本関係の活動をしています)
国立国会図書館国際子ども図書館・長野県立図書館・長野市立図書館などに納本されましたでしょうか?図書館に納本しておくことが記録として残すには大事なことですね。
絵本『にとはちさん』をとおし、子どもたちに、今の自分たちの命が、このような人たちによってつながってきたことを知ってほしいですね。これからのご活躍を祈っております
メッセージありがとうございます。
嬉し過ぎて、何度も何度も読んでしまいました。
日頃、顔を合わせる間柄の人たちからは、絵本の感想を聞くことはありますが、新聞等を見て絵本を買ってくださった方々等、私の知らないところでの反響が全くわからなかったので、すごくすごく嬉しかったです。
私も一昨年父を亡くしました。生前父が大事にしてた物や、夢中になっていたことなど、今になって父がどんな気持ちでそれらを大事にしていたのか、知りたくて知りたくてたまりません。
攪上さんも、きっとそんな思いで「にとはちさま」の絵本を手に取っていただいたんだと思います。
第一回のにとはちさま公演に携わっていただいたお父様。
その当時の方々の活躍がなければ、今のにとはちの活動もなかったはずです。
本当に、たくさんの方たちに支えられて、今があるんだなぁ、、、とありがたい気持ちで涙が出てきます。
いいお話をありがとうございました。
そして、わざわざこうしてメッセージを届けてくださったこと、本当に本当に嬉しいです。
コロナ禍で、演劇活動が出来なかった期間中、何とかして「にとはちさま」を伝えて行かなければ!と思いました。このまま演劇活動が出来なくなってしまえば、にとはちが消えてしまう。演劇以外の方法で、語り繋いで行くには、絵本だ!と思い立ち、無我夢中で書きました。
にとはちさま保存会は、仕事量の多さから年々、地域やPTAの協力がほとんど得られない状況が続いています。
いつの日か、保存会が消滅したとしても、形として絵本を残すことで、自分たちがいなくなった未来にも語り継ぐ事が出来るはず。
そんな思いを込めた絵本です。
攪上さんに、その思いを受け取っていただいたような気がして、本当に嬉しい(T-T)
お名前の読み方がわからず、Googleで検索したところ、、、びっくりしました‼︎
攪上さん、素晴らしい活動をされていらっしゃるんですね。
「にとはちさま」を見つけてくださって、本当に感謝いたします。
ステキなメッセージを送ってくださり、ありがとうございました。
内田ちづる